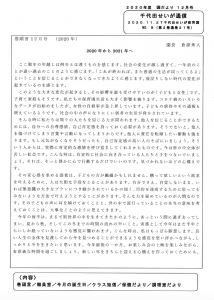昼食を子どもたちの隣で食べていたら、鬼滅の話で盛り上がっている時がありました。登場人物の名前当てクイズだったり、どうやって鬼をやっつけるかということだったり。そばで聞いていても、何が面白いのかよくわからないのですが、なぜか鱗滝左近次だけは「さん」付けだったりして、彼らの身近な物語になっています。私が生まれたのは1960年。その頃はすでにモノクロテレビが家庭に入り始めた頃。すでに子ども向けの漫画週刊誌もありました。それ以降に生まれた人は家にテレビのない生活を想像することは難しいでしょう。ましてや明治時代や江戸時代、さらにはそれ以前の子どもが接することができる物語といったら、家の人が語ってくれる民話ぐらいしかなかったはずです。その村に言い伝えられてきた「村ばなし」(松谷みよ子)が、主流だったのでしょう。
そのモチーフは、飢饉、疾病、戦争がほとんどです。いつも腹を減らし、ひもじい思いをして暮らしていく知恵や教訓が「言い伝え」られていったのでしょう。民話を聞き集めている小野和子さんが、次のような話を紹介しています。
「ひどい飢饉に見舞われた年のことだ。旅人がある家を覗くと、みんなで蕎麦を食っていた・最後の食糧として残しておいた蕎麦の実を挽いて蕎麦を作り、それを食っていたところだという。そして旅人にもそれを振る舞った。思わぬご馳走に出食わして、旅人は喜んでそれを食うと、礼をいって歩き出した。しばらくいくと、手に鎌を持った男に出会った。つい、蕎麦をご馳走になったことを話すと、男は「食ったあと湯を飲んだか」と尋ねた。「急いでいたから水だけ飲んできた」というと、男はやおら持っていた鎌で旅人の腹を裂き、なかから蕎麦を引っ張り出して、がつがつと食ったという。蕎麦は湯には溶けるが水には溶けないのだ。」
「だから、腹の中の食べ物を誰かに食われないように、物を食った後は必ず湯を飲めよ」と諭してこの話は終わるのだと言います。
こんな話が語られていた時代の切実なテーマは飢餓の中でどうやっていきのびるか、だったのです。確かに今の時代は飢えて死ぬことはなくなったかもしれません。しかし、病気や病原体の危機は現実に進行中です。その状況を民話にすることはしませんが、小説や映画や音楽やコミックの中の「メッセージ」になって、文化現象を産んでいると捉えれば、これらが現代の民話なのかもしれません。