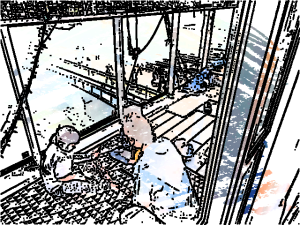
今朝の子どもの様子を先生と話し合っているうちに、子どもの主体性の話になりました。朝からベランダで遊んでいた子どものことについて、その経緯を知ると「なるほど!」と思ったからです。どうしてそこで先生と遊んでいるのかという経緯やそこに至るまでの「姿の背景」を知ることで、見えてくるのが<子どもの主体性>(あえてこの言葉を使うなら)というものだなあと感じたのです。この説明はちょっと伝わらないかもしれませんが、こんなことです。
主体性という概念は実は関係性の状態のようなもので、固定的な個人の能力や属性ではないのではないかと思いえます。確かに行為主体性の進化や発達が論じられているので、個人にも実態としてあるような気になるのですが、実際は主体である子どもがさまざまな要因の複雑な契機のなかで見せてくれるものであり、川田学さんがいうように「つながり」のなかで現れてくる関係の変容だと捉えた方が保育の実際にあうようなきがします。
また子どもがそのようにあるということは、子どもが最終的に一人で(自己)決定したことではなくて、何かを選択などして、たとえそのように見えたとしても、さまざまな要因との相互作用のつかのまの揺らぎのなかでの動的平衡状態のようなものにも見えてきます。こっちをやっていたかと思うと次はこうというように、変幻する流動体のなかに主体という焦点を探そうとしても、同定しにくいように感じます。
たとえば今朝、先生との「・・・それじゃあ、しらばらくベランダで絵本でも読んでみる?」という提案があったからこそ、その子はそこを選んだのであり、さらにその提案を生んだのも当の彼女の姿への配慮からだったわけで、さらに遡ればその姿になったのも、一緒に遊んでいた子どもとの積み木をめぐる遊びの展開のなかで生じたことがきっかけになっています。また話し合って決まったということが何かあったとしても、そのなかには子どもたちなりの主張や妥協や同意や諦めなどが渦巻いており、いろいろなことがあっての、その状態だからです。
子ども理解の背景をしるということは、その動的変化の隠れた要因がみえてくるようなものであり、そこにもう一つの太いラインがあったのかと気付きつつ、そこを辿り直すようなことが物語としてみえてくるという仕掛けになっているのかもしれません。









