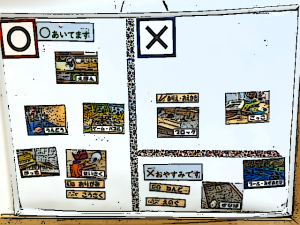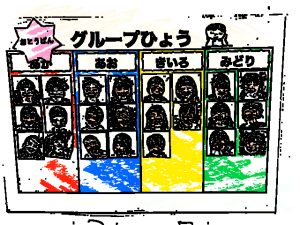どんな卒園式にしたいかを子どもにきくと「楽しい卒園式」という言葉がでてきます。その「楽しい」の中身は子どもによって異なるかもしれません。ところが、大人がイメージする卒園式の場合に「楽しい」が入ってくるかどうか? 12月に開いた「お楽しみ会」なら、劇遊び、ごっこ遊びをご家族と一緒に楽しむという「ねらい」があるので、まさに「楽しい」というイメージと一致します。私たち大人が卒園式や入学式にこめる思いは、重みがあります。子どもたちにもその重みを感じています。それがどこからくるんだろう?と考えると、やはり、この生活がもう直ぐ終わるという予感から現実に向かっている時間がそうさせていくように思えてきます。
何かが終わって新しい何かが始まるというのは、存在し続ける生命(いのち)の特徴です。あり続けているのに、個体は一生という時間を生きる運命になっている、その生と死の循環の縮図を、入学や卒業というセレモニーは醸し出してしまうものに、思えてきます。それは去就と再生の儀式にどうしてもなっていくのでしょう。
今日は2回目のリハーサル、といっても通しでやってみたのは初めてですが、「ちょっと緊張した」という言葉もありました。練習を始める時、私はすいすいさんたちが主人公だよ、どんな式にしたいか、ともう一度聞いてみました。それを自覚できるようになってきているからです。自分たちで思い通りの楽しい式になるといいね、という気持ちを込めたのですが、夕方からの会場準備には本人たちも家具の移動などをせっせと手伝ってくれて、それがとても楽しそうでもあり、頼もしい限りでした。
式の中には子どもたちからの「呼びかけと歌」があります。その歌の一つは「イノチノマーチ」で、こんな歌詞です。
🎵 飛び出すぜ 心はどこへ 水の中 地図の外
はじまりだ いま おわらない もう
命のマーチ 水平線に
鳴らせ 無限の ファンファーレ
この歌を担任がふだんから子どもたちと一緒に歌ってきました。マーチに合わせて歩んでいく私たちのそれぞれの人生は、地図にも載っていない、行き先の見えない旅のようなものです。
でも私たちは最初から、なぜか、もうすでにここにいて、はじめっているいることに後で気づくのですが、それは終わることのない「いのちのマーチ」でありながら、喝采を集める今の連続でもあるのです。
卒園式は、みんなで讃えたいので、日曜日の開催です。