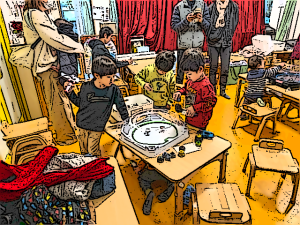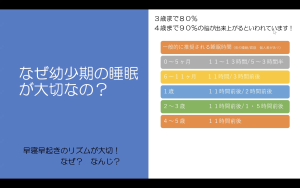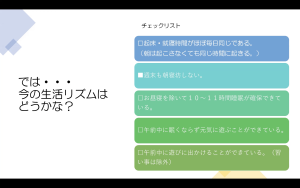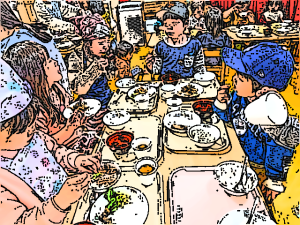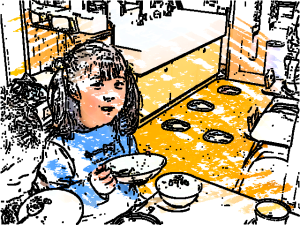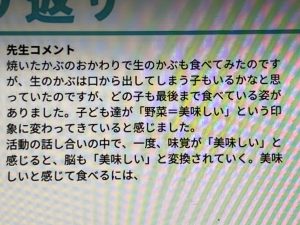今日と明日は、保育環境研究所ギビングツリー(当法人の理事長である藤森平司が代表を務めている保育研修団体)が主催する「リーダー研修」です。午前中は保育園見学で午後から高田馬場の会場で研修です。当園にも3園5名の見学がありました。
園の主任やリーダーが参加しているので、テーマは組織マネジメントが大きな柱になります。園全体の保育の舵取り役として、園長から期待されている役割も重く、抱えている課題や悩みも大きなものがあります。
ある意味で保育で大事なのは実行しているかどうかです。いいなと思ったことが保育として実現できているかどうか。研修を受けたりして、いろいろなことを学んだとしても、それが実践され、良い変化が生まれていなければ意味がありません。何が良い変化かを短期的に見極めることは難しいかもしれませんが、それでも、その兆しや傾向は感じることができるものです。
しかし、それが大事なことだと気づいても、それが実現できるかどうか、その「ここ」と「そこ」の2つの間には溝なりギャップなりが、横たわってています。しかもそれはいろいろあります。やりたいことと現実、自分と他者、思いの違い、伝わり難さ、見えない壁、あるいは落とし穴・・いろいろな溝なりギャップなりが、いろんな形で課題にみえるようなことが、保育の仕事には付きまといます。人間関係の問題というような言葉で語られることも含まれます。
それはどうやっていくと、それが埋められていくのでしょうか。なにかの理解不足と言うこともあれば、意欲や熱意の個人差だったり、あるいはコミュニケーションのあり方が問題だったりするかもしれません。今回のリーダー研修にかぎらず、毎回話題になる、ある意味で永遠のテーマかもしれません。
それでもある程度の鉄則というか王道があるように思えます。それは目指す保育の理念や方針という「のぼりたい山の姿」がなんとなくでも共有していくなかで、相手を変えようとするよりも、まずは自分が変わり、周りが真似したい、そうなりたいと思われるような立場になるように自己を磨こうということ。さらに、どうしたらいいのかはまず自分がやってみて、どうしたらいいのかをわかりやすく示すモデルになっていくこと。そして、誰もがもっている「よさ」を見つけ出し合い、リスペクトしあい、楽しい職場にしていくこと。
なかでも「リーダーは人格を磨くことが欠かせないと思う」(新宿せいが子ども園のM先生)という言葉に共感する参加者たちでした。