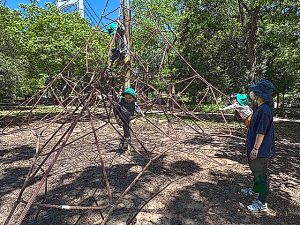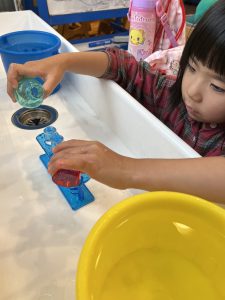私たちが立ち帰るものに保育原理があります。そこに書いてあることは、長い年月をかけて先人たちが作り上げてきた教育や保育や育児の要諦が、簡潔に記載されています。大事な原理、原則のようなもの、あるいは保育の道標のようなものになります。こういうことが起きていて、どうしたらいいのだろうか、どう考えたらいいのだろうか、という時、私はまず、「保育は養護と教育が一体的に行われている営みである」という保育所保育の特性に立ち帰ることにしています。

養護は生命の保持と情緒の安定ですが、そのためにはさまざまな欲求が満たされていく必要があって、とりわけ社会的な欲求、つまり人と人の関わりの中で見えてくる欲求、社会的な欲求が十分に満たされていないと、とかく不安定になりがちです。どんな関わりの欲求なのだろうか。それはケースバイケースです。
それはある時は愛情かもしれないし、私をみて「これ作ったの、みて」と認めてもらいたいという承認の欲求かもしれません。あるいは自分でやりたい、思う通りにしたい!という自在感のようなものだったり、何かを成し遂げた時の達成感のようなものの時もあるでしょう。また、お友達という仲間の一員になりたいという仲間意識、所属感のようなものも、あるかもしれない。
規範意識が育ってきたからこ生まれる葛藤もあります。自分はきまりやルールを守っているのに、そうじゃない姿を目にすると「違う」と言いたくなる気持ち。そうすることになっているという事を守れないお友達への注意をめぐって、手が出てしまうこともあります。公平感や正義感からくる「守らないのは悪いこと」という意識から、強い働きかけが生まれてきます。指摘されて「あ、そうだった」と、行動が変わればいいのですが、そう簡単にはいかないものです。それができるようになるまでに、ある程度の時間がかかります。
とにかく、いろいろな「思い」の伝え合いの中で、それが子ども同士の中でぶつかり合ったり、受け損ねたりし、誤解しあったりすること、やりとりしている間に、こんがらがってしまってうことも起きます。子どもたちは、幾つもの「こうしたい、ああしたい」が絡み合って、それぞれの主張がぶつかってしまう時もあります。さらに感情的になって、気持ちを抑えきれず、手が出てしまうこともあったりします。
子どもは「やり方が違うよ、こうだよ」と優しく教えることができず「違うよ、ダメだよ」という強い言い方になることもしばしば。それを無視したり応えたりしないと、伝えた方が「制裁」への向かうことがあります。先生に言いつけにくる、といこともあります。守ってほしいルールは子どもがやることなので単純明快な方がよくて、人を叩いたり(バンしたり)、蹴ったり(キックしたり)、噛み付いたり(ガブしたり)はダメだよ、ということは、大体小さい時から理解していきます。それでも、相手がそうしてくると、つい自分も「応戦してしまう」ということだったあります。
このような我慢できる力や、感情をコントロールする自制心などは、持って生まれた特性や経験の積み重ねの度合い、他の欲求が満たされているか(睡眠不足とか運動不足、お腹が空いているか)など、生理的な欲求も含めて、どうなっているかという個別の影響なども相まって、いろいろなことが影響します。
先生や親の話も理解して、わかっているのですが、実際にその場面になるとまだできないということもあります。私たちは、起きた事柄の経緯から、それぞれの子どもの「こんなつもりだった」という思いを丁寧に受け止めていくこと(言葉で表現できないことも多いくて、察していくしかないことも多いのですが)を大切にしながら、伝わっていないときは、仲介して「こういうつもりだったんだって」と代弁したり、橋渡しをしたり、しています。どっちが正しかったか、ということはあまり優先しません。そもそも、白黒つけることが目的でもなく、それぞれの折り合いの付け方、気持ちの寄せ合い方、許し方、仲直りへの気持ちの整理の仕方などを、体験的に学んでいく、貴重な体験の積み重ねだと思っています。