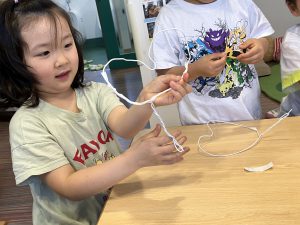(園だより5月号 巻頭言より)

生成型の人工知能(AI)の一つ、chatGPTをよく使っています。どのようなものか、実際に使ってみようと思って始めたら、私にとっては、すぐに手放せなくなりそうなくらい便利なツールになっています。例えば次のように尋ねてみます。「藤森平司が唱えている見守る保育とはなんですか?」すると次のように回答してきました。
・・・・・・
見守る保育とは、保育者が子どもたちを徹底的に観察し、子どもたちの個性や特性を理解した上で、必要に応じて手を差し伸べることで、子どもたちの自主性や自己表現力、思考力などを育む保育の方法です。
従来の保育は、どちらかというと保育者が主体的に子どもたちに指導を行うことが多といわれ、子どもたちはそれに従うことが求められていました。しかし、見守る保育では、子どもたちの興味や関心に合わせて保育内容を調整し、子どもたちが自ら学ぶ力を育むことを目的としています。
また、見守る保育では、子どもたちの成長過程を共有することが重要視されており、保護者とのコミュニケーションも密に行われます。保育者は、子どもたちの成長について保護者と共に考え、協力してこどもたちを育てることが求められます。
・・・・・・
どうでしょうか。よくこんなに平気でわかったような断定ができるものだと感心します。ネット上にある情報を集めて瞬時に回答するのですから、大したものです。藤森先生も同じことをやって「下手な解説よりも、よっぽどいいんじゃない?」と、新宿せいが子ども園だよりにも、A Iの解説を載せて、本人が間違いないと言っているから、正しいです、とユーモアたっぷりに紹介したそうです。
一方で、使っていくと、このチャットの限界もわかります。回答について、さらに詳しく問い質していくと、行き詰まりが露呈します。例えば見守る保育と要領・指針との違いを聞くと、方法でアプローチが異なることがある、というので、さらにそれは具体的に何が違うかと問うと、最初の回答の言い方を変えたものに、いくつかの要素を新たに加えてきました。それはどこでもありうる保育方法でした。自信ありげに平気で嘘もつくのです。この辺りから、知らない世界のことだと、私も騙されるかもしれないと思いました。
こう言う意味での精度は、ユーザが使うほどデータ量も増え技術もあっというまに、どんどん進化していくでしょうから解決されていくのでしょう。人間が言葉や映像や記号や音など、デジタル化されうる表象は全てAIの独壇場となるのかもしれません。しかし、もちろん人間の物理的な身体性に由来するものはAIそのものでは代替できないでしょうが、倫理的問題は別にすれば、人工人体などとの融合技術は進むでしょう。それでも人間の内部で起きている事実と人間性の関係にどんな影響を与えていくのか、専門家はきっと、そこの周辺を真剣に議論していることでしょう。