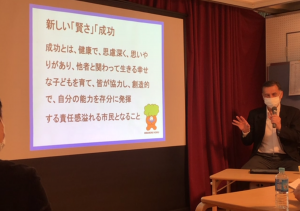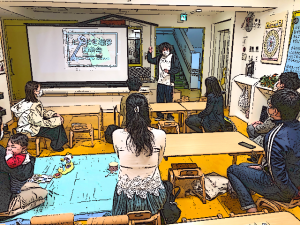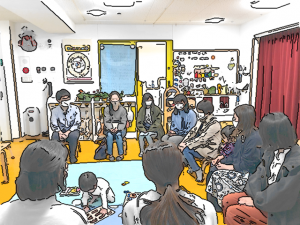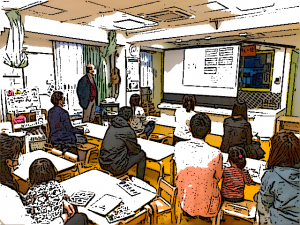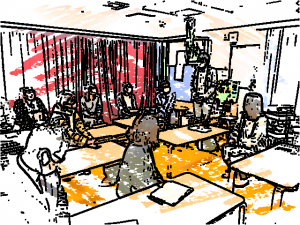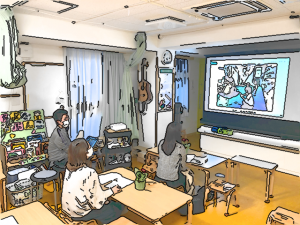◆らんらん組の保護者会を終えて
らんらん組の正式名称をご存知ですか?と言う質問には、予想通り(!)、ほとんどの保護者の方が「ぽかん?」とされていました。正解は「みんな なかよく らんらん組」です。お友達との仲の良さが、いろんなところで見られるのが年中さんの特徴なんです。そんな話から、子ども同士の関わりが、どのように心を育んでいくのか、という話をさせてもらいました。植物の生長が土壌の栄養と日光と水によって変わるように、人も持って生まれたものが、環境によって大きく変わります。心の発達の過程を踏まえると、満4歳になった子どもたちが、満5歳になっていく1年間は「社会的な心」の成長が著しい時期なのです。

今日お伝えしたことは、人の心の育ちの筋道です。0歳児の基本的信頼感の獲得から始まって、1〜2歳児から始まっている他律ではない自律を経て(基本的生活習慣を身につけていくプロセス)、それと伴奏するように自我の芽生えに伴うイヤイヤ期に見られるような自発性を発揮しながら、お手伝いなどの利他的行動を好む「自立心と協同性」の時代を経て、さらにしっかりとした道徳性や社会性を身につけてくまでの流れを、ごくごく簡単にスケッチしました。この話は、詳しくお伝えしたい子育ての秘訣が含まれる「発達の原理」なので、講演会を開いた方がいいかな、と今日話しながら感じました。詳しく聞きたいという方がいらしたら、いつでもやりますので、担任までお声かけください。
と言うわけで、幼児期の真ん中にある「らんらん」は、まさしく「自立心と協同性」の時代にいます。やってあげることが、楽しい時期に入っていきます。集団のある保育園生活の中で、案外、最ものんびりとできる1年かもしれませんよ。それだけに、何があったんだっけ?と終わってしまいがちな年中さんかもしれないので、見逃さないように、よーく、観察してみましょう。とても面白い成長を見せてくれる一年ですから。
こうした心を耕す体験は、保育園ならではのものです。全ての子どもにこの時代を過ごさせてあげたい。学年別のクラスや学校的空間では、自由遊びの中での子ども同士が織りなす体験は生まれにくいのです。ああ、もったいない。子どもたちもまた自然の一部であり、そこには、その奥深い「子ども社会」が生まれています。もし、そこに大人の指図が過剰に割り込んでしまうと、微妙なバランスで成り立っている自然の生態系が乱されてしまいます。それだけは避けてあげたい。本当にこの時代に必要な体験を保障してあげたい。それは不思議なことに、子ども同士の社会が、自分たちで作り上げていくものなのです。
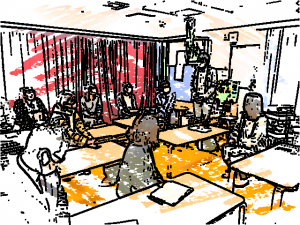
自己紹介も楽しいものでした。ありがとうございました。お子さんの「よさ」をいっぱい見つけてあげてください。その数だけ、子どもは幸せになるでしょう。親御さんがいいなあ、と思っていることがきっと伸びていくんじゃないでしょうか。まるで新緑の芽が太陽を向くように。いいね、と認めてもらえることが最高の栄養になりながら。一緒にその一つ一つを愛しんでいきしょう。