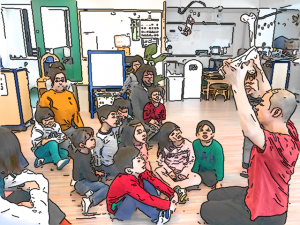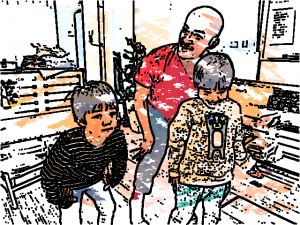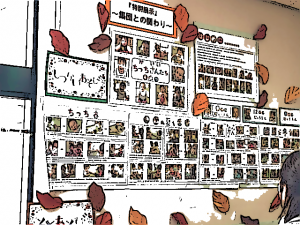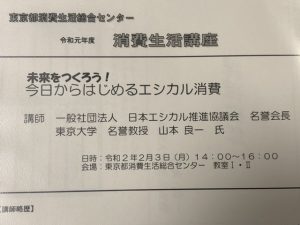「これからの保育園入園を控えているため、それに向けての生活リズムの心構えができた。夜泣きのタイミングやその改善方法が知れてよかった。常夜灯NGがわかったのは、とてもよかった」
今日の参加者の感想です。保育園生活が始まるというのは、育児休業中の保護者の方も仕事が始まることになるので、子どもの生活リズムも変わってきます。今よりも朝起きるのが早くなり、仕事から帰ってきて晩御飯を食べさせてお風呂に入って、8時半にはお布団に入って電気を消して・・そうした生活リズムを作っていくために必要な準備がとっても大切な時期です。それをどのようなことから始めたらいいのか。今回はその「逆算マネジメント」のコツを中心に、ポイントをまとめるような会になりました。
理想の睡眠サイクルになるまでのポイントを、私なりに、まとめてみました。
(1)夜の睡眠は10時間から11時間が必要。
これは0歳から小学生になるまで同じです。夜の睡眠時間を10時間確保しようとしたら、朝7時に起きても夜9時には寝ないと確保できません。小学校は朝8時15分に着席していることをイメージすると、歩いていく通学時間を考えれば7時何分に家をでる、すると何時にトイレを済ませ、何時に食事を済ませ、何時に起きないと間に合わないか。小学生になるまでを見通して、今から生活リズムを整えるようにしましょう。
(2)逆算マネジメントで生活リズムを作ろう。
朝起きる時間が決まれば、そこから11時間の睡眠を確保するには何時に寝る必要があるか。夜8時か8時半か9時か?そこから逆算すると、何時に布団に入るか。ツンツン・ごろこごろ・心のスキンシップの時間を考えて何時に食事を済ませるか。何時に夕食の準備を始めるか。何時に保育園にお迎えに行くか。
(3)お昼寝の時間を補って11時間にするのではない。
夜の睡眠は特別であり、それ自体として確保しないといけない。足して11時間になればいいというものではない。夜の睡眠が確保できるように、お昼寝は調整すること。
(4)お昼寝を短くして夜が良く寝るならそれでいい。
3歳ぐらいまではお昼寝をしても夜ちゃんと11時間寝ることができる。4歳以降から昼寝が長過ぎると夜の睡眠が短くなってしまうリズムの崩れがあるなら、お昼寝は短く、あるいは無くしたほうがいい。そこには個人差があるから、一概に何歳だからとか何時間だからということはできない。
(5)日本人は世界の中でも睡眠時間が短い。
子どもも短い。子どもがよく寝ている国は北欧とニュージーランド。北欧は学力も高い。睡眠と生活リズムと学力の高さにも相関関係が見出せる。中学生も夜9時には寝ている。単に勉強時間が長ければ学力が良くなるという関係は疑わしい。
(6)夜の睡眠の質が高いと、昼間の活動や学びの質も良くなる。
学校での学習の質が高くなり、脳の集中力とか、主体的に考えることなどの質と影響する。
(7)睡眠には質の違いがある。
最初の深い眠り(ノンレム睡眠)の時に、成長ホルモンなどが出る。明かりの影響が最初の眠りの質を貶める。睡眠は単なる休憩ではない。脳を育て、知識を定着させ、神経細胞を整えるなど、多様な役割がある。
(8)夜の睡眠をよくするには24時間の生活リズムが大事。
午前中に活発に活動する。脳は10時から12時にもっとも活動できる。夕方から脳は眠りたいタイミングに入る。
(9)寝る部屋は基本、真っ暗にすること。
常夜灯は不要。夜起きて何かするときだけ。エアコンや空気清浄機の電源の点灯や、加湿器のほの赤い灯などもタオルをかけて口のところだけ開けて使う。
(10)眠るホルモンの分泌を妨げる青白の光
昔のブラウン管テレビと今のとは光の性質が異なり、青色や白色が多いので子どもの脳は、それに依存するようになり、覚醒させてしまう。その光の影響はテレビよりもスマホ、スマホよりもタブレットの方が影響は大きい。
(11)小児科学会は、いつであろうと2歳まではテレビはNG。
これは世界の常識になっている。日本はいつの間にか忘れられているかも。もし見るなら親子で双方向性を保つように見ること。子どもが受動的に受け身で見るだけはよくない。

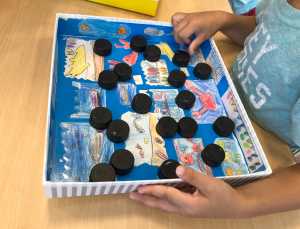
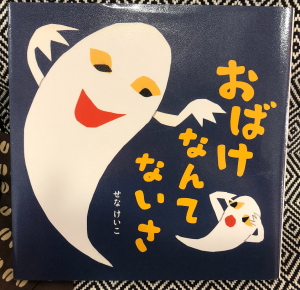











-300x191.png)