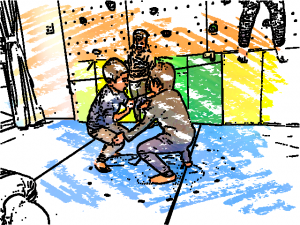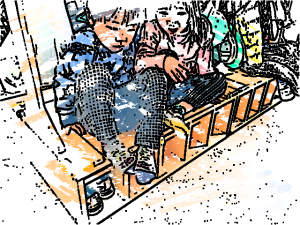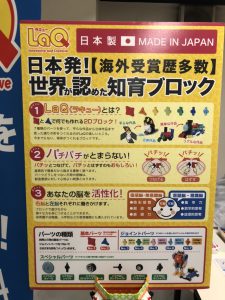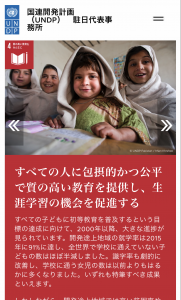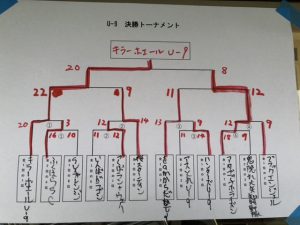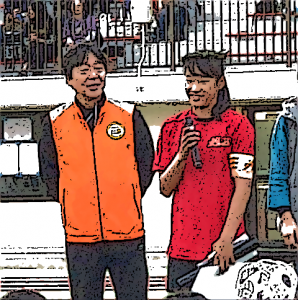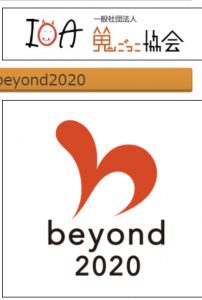「お祭りなんだから、さあさあ、呑んで呑んで!」

(17日の科学博物館で)
今年5月の神田祭の神輿神霊入れの座で、石渡さんにお神酒を勧められたことを思い出しました、「せっかくだから奥の席に座って」と。それは有り難いお誘いでありながら、こんな時間から飲むわけもいかないので、その旨を言い訳にすると「お祭りなんだから、無礼講でいいんだから」とその方はおっしゃいます。
嬉しいやら困ったらやらで、曖昧で煮え切らない、いかにも無粋な様子だったのでしょう、そばから「園長先生はまだこれから仕事なんだから、無理にすすめちゃダメだって」と救いの手を出してくださったのが、ちよだリバーサイドプロジェクトの岡田さんでした。まだ夕方の4時過ぎだったので無礼を詫びて園に戻ったのです。
忘年会やら懇親会やらの時期になりました。会社勤めの私たちには、こちらの方が「祭り」の気分を味わう機会かもしれません。ちょっとだけ「無礼講」の要素がありますよね。ちょっと寄り道します。
社会科学の学問によると、お祭りは定住社会になってから生まれました。その社会が生み出した言葉と法の中で毎日を過ごしていると、それは本来的に不自然なものなので、徐々に生命力が枯渇していきます。日本では「気=生命力」が枯れるという意味から「ケガレ」ることとみなされます。
そこで、日常世界の外側、人的社会の外側への接点を求めて、そこから生命力を呼び込んで回復しようとします。そこに聖なるもの、大いなる異質なるもの(自然や神や被差別社会)を呼び込み、穢れを晴す「ハレ」なる祭りを企てるのです。その時は、平時のルールは破られるので無礼講というわけです。「お酒の席ですからお許しを」というのも、似たような起源でしょう。
1960年生まれの私などは、その掟を破ってもいいという感覚、お祭りのキワドサの消息を皮膚感覚で知っています。私の小6の担任の先生は「おくんち」というお祭りに連れて行ってくれたのですが、その時、先生らしからぬ、普段は見せないある行動をしました。それはここでは言えませんが、私は小学生ながら「お祭りだと、それくらいは許されるんだ」ということを学びました。
ハレとケの世界を行き来することは、とても危険なことだったので、そこには心を鎮めるための儀式を必要としました。それが神輿だったり、お囃子だったりするのです。こんな経緯を抱えているのが、文化的歴史の中で生きている私たちの「心」なのです。
さて、寄り道から戻ると、本来子どもは、自然そのものです。異質な存在です。養老孟司さんに言わせると「子どもは自然だってことを、大人は忘れている。自然はいいなりにならないものと心得たほうがいい。デコボコの山道で転んで山に文句を言う人はいないでしょ。都市の平らなアスファルトの道を歩くことと同じように、子どもの安心、安全にばかり気を使い、言うことを聞く子にしたがっている」ということになります。
私には子どもは、赤ちゃんの頃から危険を回避する力を持っていて、大人をハレに導く力さえ持っているような気がします。大人が子どもの危険回避能力を奪っているのではないでしょうか。
昨日17日は、わいわい、らんらんの子どもたちが上野の科学博物館にバス遠足に行っています。その様子は「クラスブログ」で紹介されています。私は行けなったのですが、自然の存在である子どもが博物館で何に共振するのかということに興味があります。その私なりの「目撃」は次回に持ち越しです。

私は保育園を子どもたちのための「遊びのミュージアム」にしたいと思っています。子どもたちが、科博で何に着目しているのか、どんな印象を持ったのか、知りたいところです。子どもたちにとっても「ハレ」を感じる何かがあるんじゃないかと。