◆「子どもが落ち着いていますね」

今日は2組の親子に入園の案内をしました。0歳と2歳です。「子どもたちが落ち着いてますね」。そう言われてみて、改めて思いめぐらしたことがあります。それは「心が落ち着いているとは、どういうことか」 ということです。
◆安定した気持ち

では、同じような意味をもつ表現を集めましょう。連想ゲーム、言葉遊びです。
・・・・・
心が満たされている。満足している。
やりたいことができている。
不安もない。
愛されている。
認められている。
目的が叶っている。
仲間がいる。
喜んでいる。
・・・
こんな気持ちでいられたら、それは幸せなことです。確かにそんな時、子どもは落ち着き、いい顔をしています。今日は「心の解放」と「安定した気持ち」の関係について考えます。

◆情緒の安定とは・・・
こんな状態を、私たち保育士は「情緒が安定している」といいます。先ほど述べた心の状態を別の言葉でいうなら、安心、愛情、承認、達成感、連帯、歓びでしょうか。これらに共通するのは、一人では得られない社会的なものだということです。人間関係の中で初めて、得られるものです。一人で得られるものではありません。社会性とは、人間関係を上手くやる力だと思って、ほぼ間違いありません。それなら人間性とは、豊かな社会性のことになります。

◆欲求が適切に満たされるから
さて、満たされるから満足するような心の動きを、「欲求」と言っていいなら、欲求が適切に満たされるから、情緒は安定するのです。もし気持ちが穏やかでないなら、その人は何かの欲求が満たされていないのかもしれませんね。
実は、子どもも同じことです。赤ちゃんの頃から、安心した気持ちでいること、愛されること、「見てみて」というとちゃんと応えてもらえること、「やったあ、できた、できたぁ」って嬉しがってもらえること、そばにいるのが親しい「お友だち」であること、そして友だちが楽しそうだと自分も嬉しく思うこと。
こんな生活が確かにあります。
◆心が解放されると心は落ち着く
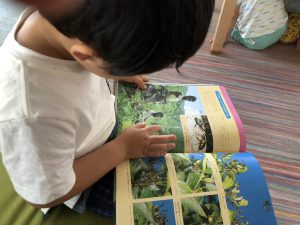
この「情緒の安定」が図られことを、別の言葉でケアといいます。養護のこと、世話をする、配慮すると言った方がわかりやすいでしょうか。先生たちは、のびのびと心ゆくまで、やりたいことが出来るように、子どもたちの欲求に応えています。先生たちはどこまでも優しく穏やかで、寛いだ雰囲気を大事にしてくれています。だから、子どもたちは落ち着いているのでしょう。
◆心の解放も欲求の一つ

そうすると、欲求に応えてあげることは、心を解放することも含まれてることになりますね。
だだし、大切なことを忘れてはいけません。それは、家庭でもここで申し上げたことをやってくださっているからこその園生活だということです。家庭での落ち着いた生活があって初めて、落ち着いた園生活になるからです。
情緒の安定は、実り多き学びに直結するのですが、その話はまた明日。内発的動機が生じる仕組みについてです。









