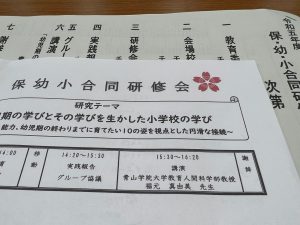この「園長の日記」は、あくまでも私からみえたもの、私が考えたことを書き連ねているわけですが、園全体の描写ではありません。園で定めた「正式な記録」は、ほかに園日誌やクラス日誌、保健日誌、給食日誌などがあり、個別やクラスの連絡記録も毎日、保護者のみなさんとやりとりしています。それらは事実でありながら「部分」でしかなく、それらを寄せ集めて、はじめて「全体」に近くなります。それでも決して<保育の全体>というものを描き切ることにはなっておらず、多分それは原理的に不可能でしょう。
しかし、だからと言って、それを放棄するつもりはなく、何を目指しているのかというと、それを積み重ねてることで、なにかしらの実相に近いものがみえてくるのではないか、それを分かち合うことで、新しい次の一歩の踏み出し方がもっとよくなるのではないか、と思うのです。

今週を振り返ってみましょう。初めて行ったことだけでも、日曜日には乳児室を開放して午前中親子で過ごしてもらいました(当日の園長の日記をご覧ください)。月曜日は某大学で夕方、うちの職員と3人で絵本やわらべうたの実践を紹介して授業をしました。火曜日は千代田保健所から調理室の抜き打ち検査があり、衛生管理はいつ誰が来ようと自信あったのですが、その通り「除去食もきめ細かく対応しておられますね」と褒められました。本当は調理の先生たちと一緒に、ほっと胸をなせ下ろしました。食中毒の季節だから用心するに越したことはありません。

その日は保護者の方から夕方、大きな尺取虫をいただき、翌日に子どもにどう見せるか検討しました。すると水曜日の朝のお集まりに、なぜか主任が全身緑色のタイツを着て青虫になっていました。尺取虫が現れて触発されたようです。私は慣れているので平気だったのですが、私が案内していた入園見学者がちょっとびっくりしていたそうで、それに気づいた別の担任が「うちの保育園はあれで動じないくらいの方に入園してもらったほうがいいですね」といい、園長の心配をよそに、意識は私の遥か上空にあることを確認しました。
この時期は「蚊」対策も始まります。東京都が午後に研修会を開きました。日本は亜熱帯になってきて、蚊を媒介する伝染病の患者が見受けられるようになってきたから注意してください、という内容でした。ここにも温暖化の影響です。屋上の野菜も育ち、毎日のように「大葉」を摘んでは調理さんや私のところへ持ってきます。
木曜日は3〜5歳が梅雨の合間を縫って地下鉄で十思公園へ出かけました。今年度初めての試みです。楽しかったあ、と帰ってきた子どもたちは「また行きたい」と言っています。朝は毎月の避難訓練もあり、地震から火災が発生、園内放送をよく聞いて指定の場所へ避難します。合言葉の「おかしも」もすっかり定着しています。午前中に協力している活動のイベントのフライヤーを近くの公設機関へ届け、午後は姉妹園で会議に出席。夕方戻ってきて、保護者の方々と一緒に7月の納涼会の内容について打ち合わせでした。
そして16日金曜日は歯科検診。年2回ありますが、虫歯や咬合具合などを診てもらうのは大事な診察です。秋には歯科医に講演をしてもらうつもりです。検診結果は必要な方へお知らせしました。また午前中は昨日につづき、幼児は選択で十思公園へ出かけています。乳児は小川町や和泉公園へ出かけ、花を摘んだり虫を探したり、かけっこを楽しんだり。

夕方には私の絵本の読み聞かせをしましたが、いろいろな子どもの様子がわかり、また成長を感じて楽しいひと時でした。こんな具合に起きたことを並べるだけでも色々ですが、いずれにしても何をみうしたくないかというと次のことです。
私たちは、子どもに望んでいることがあって、それは乳幼児にふさわしい経験を通して、生涯にわたる人格形成の基礎が培われるように、また小学校以降の生活や学びにいかされていくように、なってほしいと思っています。しかも子ども本人が望んでいること、満たしたがっていることがあるなら、それを環境をとおして実現できるようにしてあげたい。しかも、同時にその環境が教材のような効果を発揮して、子どもが自分の育ちとして取り入れていくような、そんな幼児教育になるようにしたいのです。
私の園長日誌の役割の一つは、そのいきさつを具体的な場面でお伝えすること。さきほどのいろいろな記録を読みながら、とくにクラスブログで取り上げているエピソードに(担任が取り上げるだけの意味があるからこそ取り上げているわけですが)意味を見出していこうと思っています。
また、あまり注目されないようなことの中にも、それはあるかもしれず、意味をなす背景を探したり、一見関係なさそうなことも、保育の意味での生態学的な役割を果たしていることも十分に考えられるので、そういうことまで視野に入れたいなあ、と思っています。あまり広がると拡散してぼやけてしまうかもしれませんが。そういうわけで原理的な見方を学び、その観点から保育を見ていくことが有効だろうと考えています。
でもそこが難しい。その意味を理解するために、できるだけ保育の原理的なことに立ち返り、どうしてそこにそんな意味付けができるのかをできるだけ確かめたいつもりです。それを勉強することは時間が要ります。でもそれが私には楽しい。新しい意味に気づくと同時に、子どもが関わる環境が新しい構成へと刷新されてゆき、保育が深まっていくように思えるからです。